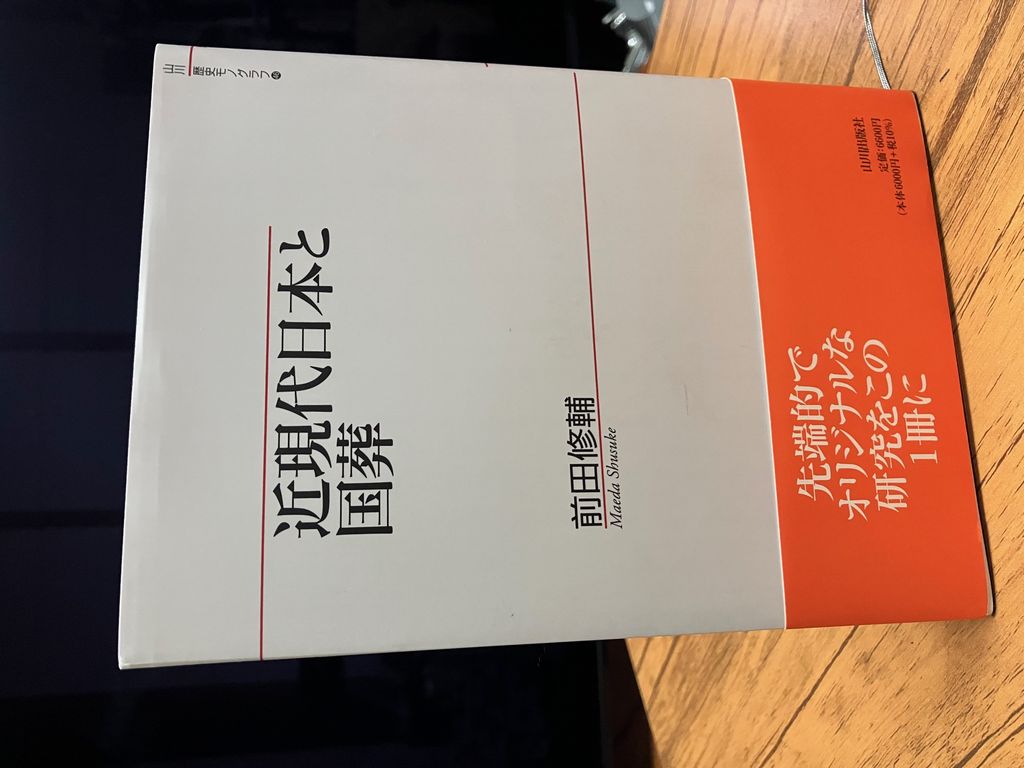|
アーカイブ 西日本新聞社編 書評 2025/01/25 豊田 滋通
近現代日本と国葬 「モヤモヤ」を晴らすために 前田修輔著(山川出版社)
2022年7月、安倍晋三元首相が奈良市で選挙遊説中に射殺されたとき、「ひょっとすると国葬論議が起こるかも」という漠然とした予感があった。同じく凶弾に倒れた明治の元勲・伊藤博文の事例が脳裏をよぎったからだ。予感は的中し、岸田内閣は閣議決定で国葬実施を決め、国論が二分される中、同年9月、日本武道館で挙行した。あれから2年半が経つが、「なぜ国葬だったのか」という疑問は今も解消されない。そんなモヤモヤを抱える方に、お薦めしたいのが本書である。
この本は、博士論文を改稿した学術書である。明治維新期の公葬と国葬成立へのあゆみ、皇室喪礼法制化と宗教の関係、法制化された旧憲法下の国葬と戦後の皇室喪儀や国葬論議の推移などを、数多くの事例で検証。豊富な史料の積み重ねによって、「国葬とは何か」「当時の政権はなぜ国葬を選択したのか」という根源的な問いに迫って行く。
学校教育では、維新の英傑や政治史の重要人物たちの業績は習っても、その葬儀がどのように行われたのかは知る由もなかった。本書は、暴徒に殺害された大久保利通の葬儀(明治11年)が神式で挙行され、天皇の下賜金や国費を投じた葬儀費用がいくらだったか、政務の休止や歌舞音曲停止などの服喪形態、弔砲や儀仗兵の数、葬列の組み方、会葬者の服制など「国葬の原型」がどのように形成されたかを克明に分析。対外的に「初の国葬」となった岩倉具視の葬儀(明治16年)と、政府公告で「公式に国葬」と位置付けられた三条実美の葬儀(同24年)を経て「国家偉勲者に対する最大級の栄典」である国葬が確立されて行った過程を明らかにする。
事例研究では、戦意高揚のため「全国民参加型」の国葬となった戦時下の山本五十六の葬儀や連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の意向に神経を尖らせつつ行われた新憲法下の皇室喪儀も興味深い。
著者は、国葬を「その時代を、ひいては近現代日本を鮮やかに写す鏡」だという。法的根拠が乏しい中、国会論戦もなく「憲政史上最長の在任期間」などを理由に挙行された安倍元首相の国葬が、どのように時代の実像を映していたのか―。今一度考えさせられる本である。
【著者略歴】まえだ・しゅうすけ=福岡県生まれ。上智福岡中学高等学校教諭。主要論文に『戦後の国葬論議と栄典』(「歴史評論」888号)『戦後日本の公葬―国葬の変容を中心として』(「史学雑誌」130編7号)など。
| |
|